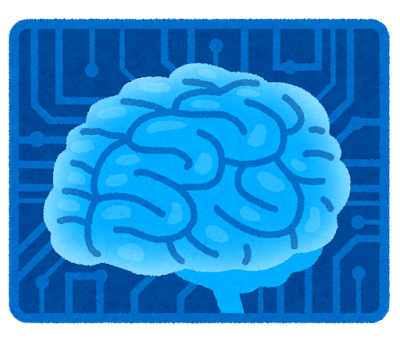生成AIの普及に伴い、著作権法、特許法、意匠法、商標法といった知的財産法との関係が大きな論点となっています。以下では、各分野での主要論点を整理します
1.生成AIと著作権法
学習データとしての著作物利用
生成AIの性能向上には、大量の著作物を学習データとして用いる必要があります。
著作権法第30条の4は「情報解析目的」での著作物の利用を一定範囲で許容していますが、
• 営利目的のAI学習がこれに含まれるか
• 著作物の本質的特徴を抽出する行為も許容されるのか
については、解釈が分かれており、出版社や作家団体による反対も背景に、今後の法改正やガイドライン整備が注目されています。
生成AIのアウトプットの著作物性
著作権法は「人間の創作」を保護対象としているため、AIが自律的に生成した文章・画像等には原則として著作権は発生しません。ただし、ユーザーがプロンプト設計や生成物の選定・編集を通じて創作的に関与した場合は、人的創作性が認められ、著作物として保護される可能性があります。
既存著作物との類似と侵害リスク
生成AIが既存の著作物に類似したコンテンツを出力する場合、
• 依拠性(元作品をコピーしたと言えるか)
• 類似性(実質的に似ているか)
が認められれば著作権侵害となる可能性があります。誰が責任を負うのか(AI開発者か、利用者か)も重要な論点です。
日本の現行ガイドライン
文化庁は「AIと著作権に関する考え方」(令和5年4月)で、
• 学習利用は原則許容
• 生成物は人の創作性がなければ著作物に該当しない
• 類似コンテンツが生じた場合の依拠性が問題
• 生成物の利用者が最終的に責任を負う
と整理しています。ただし、法的拘束力はなく、将来的な立法の可能性も議論されています。
2.生成AIと特許法
発明者性とAIの関与
特許法は「発明者=自然人」を前提としています。AI単独の発明は認められず、AIを補助的に用いた場合も、発明の構想に創作的に関与した人が発明者として出願する必要があります。
AIを発明者とすることを試みた「DABUS事件」は国際的に議論されていますが、日本でも現行法上は認められていません。
生成AIによる発明の特許適格性
生成AIを用いて得られた成果が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当すれば、特許対象になります。ただし、
• AIが自動生成しただけで人間の技術的寄与がない場合
• 単なる既知技術の組み合わせ
は特許要件を満たさない可能性があります。
出願実務の留意点
• 発明者は必ず人間を記載すること
• AI生成物の技術的意義を説明し、単なる生成結果にとどめない
• 進歩性・新規性を示すために、学習データや生成プロセスを明確化する
3.生成AIと意匠法
意匠の創作性
意匠法でも、「人間による創作性」が求められるため、AIが自律的に生成したデザインをそのまま登録することは難しいとされています。ただし、ユーザーがプロンプト設計や生成物の編集を通じて創作に関与していれば、登録可能です。
実務上のポイント
• 出願書類には、創作した人(自然人)を記載する
• AIの関与を明記する義務はないが、審査対応のためにはプロンプトや編集履歴の記録が有用
• 既存意匠との類似性を事前に確認し、無意識の侵害リスクを回避する
4.生成AIと商標法
ブランド名・ロゴの商標登録
AIが考案したブランド名やロゴでも、商標法上は登録が可能です。商標法は「創作主体」を問わず、識別性と他人権利との抵触の有無を重視します。
類似リスクと責任
生成AIが既存商標や著作物に酷似する標章を出力した場合、第三者の権利侵害となる可能性があります。
生成主体がAIであっても、利用者(出願人)が責任を負います。
5.パブリシティ
パブリシティ権とは
人の氏名・肖像(顔、姿)、声などを、無断で商業利用されない権利です。
著作権とは異なり、人格権や不正競争防止法と関連して保護されることが多いです。有名人の顔や名前を勝手に広告などに使うことが典型例です。
生成AIとパブリシティ権の関係
生成AIは、著名人の顔や声を模倣してコンテンツを生成できるため、無断で作成したものがパブリシティ権の侵害となる可能性があります。
例えば、有名人のそっくりな画像を広告に使うと、本人の許可なく経済的価値を利用する行為となり問題です。
さらに、肖像や声の「学習データ」に本人のパブリシティが含まれる場合、それをどう扱うかも問題です。
まとめ
生成AIの活用は知的財産法に新たな解釈と制度整備を迫っています。
著作権、特許、意匠、商標それぞれで「人間の関与の程度」「責任主体」「既存権利との衝突」が共通の重要ポイントです。
企業や個人が生成AIを活用する際には、現行法の限界とリスクを理解し、関与の記録や利用ルールの整備が不可欠です。